気になる地元の天守再建願望
2025年から天守台の発掘調査が行われ、何らかの報告が市の教育委員会から出されると思います。福岡城に天守があった、なかったの論争は、われわれ城郭愛好家にとってロマンのある話題の一つになっていますが、気になることもあります。地元の経済界に顕著な天守再建を市に求める動きです。これを地元マスコミが積極的に報じることで天守があったことが前提になり、外観に根拠のない模擬天守が作られる可能性です。私は過去に建造された全国の模擬天守自体は時代の要求として否定的にとらえてはいないのですが、令和の時代に新造されるのは、好ましく感じません。もちろん、天守の指図や絵図が奇跡的に残っていて外容が判明した場合は別ですが、有った・無かったが議論されている中で、想像上の天守を復元するのは如何なものかと思います。報道によれば、「福岡城天守の復元的整備を考える懇談会」が福岡市に対して、天守閣の全容解明に向けた史料収集や天守台の発掘調査を進めるよう提言。天守閣の復元が「極めて困難」としている市の整備基本計画の見直しも求めたそうです。

「福岡城天守の復元的整備を考える懇談会」が用いている福岡城天守の復元CGは非常にリアルに見えるのですが、大阪夏の陣を描いた、いわゆる「黒田図屏風」がベースの大阪城天守の復元図をベースにしていると推測します。これは、豊臣氏の大坂築城に深く関与した黒田氏との関係性から推測された復元図であるのでしょう。五重の天守とすれば時代的にも、望楼型の建物が推定されますが、この復元図では大入母屋屋根が三重目の屋根に架けられており、下層の1.2.3重が順次逓減している層塔型のような外観になっています。一般に望楼型で五重天守規模の場合は、最下層の1重目とその上の二重目は概ね同大の平面が基本になっており、その上に3重(又は二重の)望楼部が載るのが通例です。同時代で例を挙げれば、岡山、広島、姫路、松江、萩、米子城あたりで、例外なのは1608年の岩国城唐造り天守(4重)と1601年頃の熊本城(初重と三重目に大入母屋)くらいです。
岩国城は年代的に福岡城より少し下がり、熊本城は、五重の天守と呼びたいのですが2重目と4重目を屋根と数えず三重と表記されることもあり、福岡城のCG復元図とは似てもいないため、事例としては参考にならないと考えています。
令和6年12月20日に福岡城天守の復元的整備を考える懇談会が公表した「福岡城天守の復元的整備について ― 報告と提言―」では、天守の再建が可能な外観の根拠としていくつかの絵図を示しています。それらについて感想を述べてみたいと思います。
福岡城の絵画的資料についての信ぴょう性
『九州諸城図』
これは慶長16、17年頃、毛利藩の密偵が描いたとされるもので、福岡城も複数の建築物が簡略に書き込まれています。豊前・筑前・肥前・筑後・肥後の五箇国間の城郭位置を略図にしたものです。この絵図では四重の高層建築が描かれていますが、これを真正なものとすれば五重の天守ではないことになります。よく見れば2重目、4重目に入母屋屋根が表現されているようですが、岡山城や熊本城のような外観にならなければならず、復元図として発表されているものとはずいぶん印象が変わります。福岡の地に御殿や多層建築のある城があるものとしてイラスト的に表現したものと解釈すべきで、天守の外観を正確に書き写したものではないと考えるのが妥当と思います。
『西国筋海陸絵図』
この絵図は、大坂から九州北半までの西日本を1枚の絵図に収めたもので、上の九州諸城図より姿が明瞭に描かれています。この絵図で福岡城の天守と思しきものは五重で書かれています。外壁は塗籠(白壁)になっており、初重に千鳥破風、二重目・三重目に切妻かと思われる破風があるのは着目すべきです。「西海航路図巻」が改訂されたものいわれていますが、絵図に書かれた他城との比較で、外観の信ぴょう性は判断されると思います。例えば赤穂城は天守なしで櫓が二重に、明石城は三重櫓で天守は無く、いずれも塗籠と描かれていますが、姫路城は天守が四重で破風も不正確に描かれています。おそらくは、この場所にはこのように立派な城郭がありますとの紹介程度のもので、外観はあてにならないというのが自分の見解です。この絵図はリンク先の国立国会図書館で見られます。
・『福岡城下絵図』
福岡藩吉田家五代目家老・吉田治年によって享保7年(1722)から11年間かけて編纂された『吉田家傳録』に収録されているとのことです。この絵図は、福岡城と城下を俯瞰した図とのことですが四重の天守らしき高楼と三重櫓2棟が描かれています。着目すべき外観は、天守が四重であるこ、切妻破風が表現されていることです。ただし年代的には江戸期中期であり、福岡城に高層の楼閣が軒をなしていることを誇張的に表現しただけではないでしょうか。
・『九州日報(現・西日本新聞)の記事に掲載された「福岡城大天守閣の模型」写真』
幕末期に造られたとされている模型の写真で、現物は第二次大戦で焼失しているとのことです。五重の天守で、外観仕様は下見板張り、四重目の四方に唐破風出窓を据え、最上階は廻り縁高欄なしの華頭窓を開いているように見えます。ただし、建物の骨格は大入母屋屋根を持たない完全な層塔式で、望楼式が相当とされる天守の年代とは一致せず、外観仕様は想像で作られたものと判断できるのではないでしょうか。
このように、実際に天守についての外観が参考になるものは、未だ皆無だといっていいのではないでしょうか。
想定される天守の外観仕様
福岡城では、門や櫓の傾向として切妻破風が多用されています。仮にもし、福岡城の天守を推定するなら、一、二重が同大で二重目屋根に大入母屋がかけられ、三重の望楼部分に用いられた破風の構成も千鳥破風や唐破風だけでなく、明かり取りの出窓部分などは、切妻破風の屋根が用いられた外観の天守になると思っています。
このような文を書いてみても、結局は根拠のない空想を個人で楽しむのみですから、私は福岡城の象徴的な建物を観光目的で復元するのであれば、天守台の南に威容を誇った武具櫓(両端に3階の望楼部を持った2重の巨大な多門櫓)を古写真と発掘成果に基づいて木造復元してほしいと考えるのです。
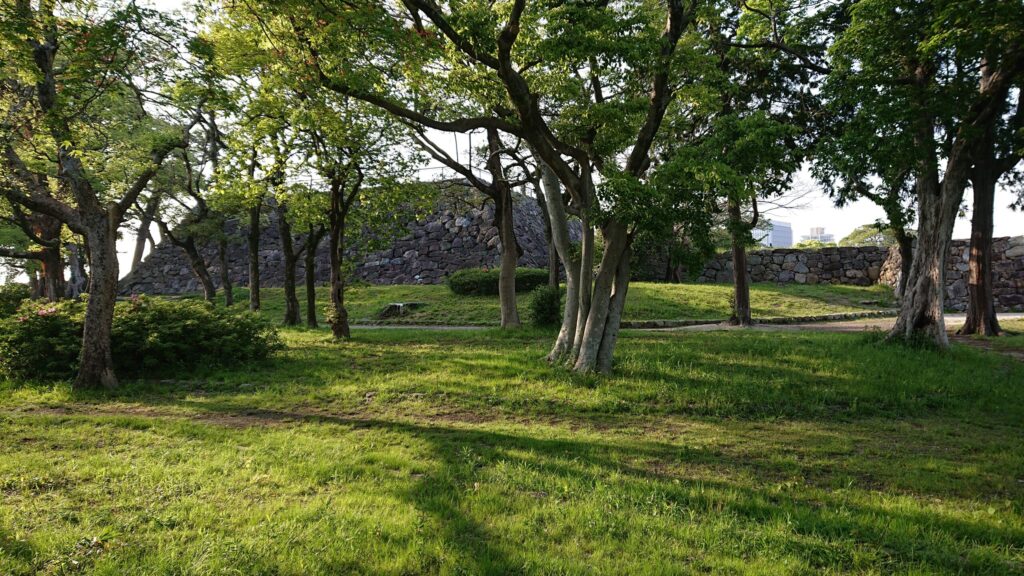
金沢城では天守を見ることはできませんが、大規模な二の丸多門櫓を木造復元しており十分に城郭探訪を楽しむことができます。古写真と発掘成果に基づいた復元建築は本物志向の現在の私たちの嗜好に合うものです。




